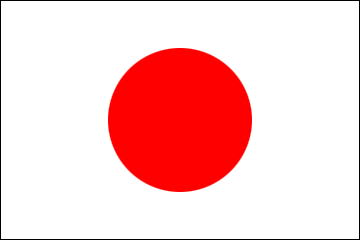届出(戸籍・国籍)
令和4年12月16日
共通事項
◎共通事項をご確認の上、下記の各届出をクリックしてください。
●個別の届出内容により、各届出に記載のもの以外にも必要とされる書類がございますので、事前に当館にご連絡下さい。
●記入漏れ、記載不備等がみられる場合には受理できない場合もあります。また、改めて訂正等のために来館又は郵送をお願いする場合がありますので併せてご了承願います。
●和訳文の作成は日本人当事者が任意のA4用紙に行うことができます。なお、必ず翻訳者の氏名を下欄に記載して下さい。
●個別の届出内容により、各届出に記載のもの以外にも必要とされる書類がございますので、事前に当館にご連絡下さい。
●記入漏れ、記載不備等がみられる場合には受理できない場合もあります。また、改めて訂正等のために来館又は郵送をお願いする場合がありますので併せてご了承願います。
●和訳文の作成は日本人当事者が任意のA4用紙に行うことができます。なお、必ず翻訳者の氏名を下欄に記載して下さい。
各届出について
婚姻届(結婚する/したとき)
日本人同士の場合は、日本国内と同様当館に婚姻届を提出することで婚姻が有効に成立します。 日本人と外国人(ロシア人を含む)の婚姻の場合は、ロシア国の法律により婚姻手続をした後、当館に報告的婚姻届を提出することで、日本人の戸籍に婚姻の事実が記載されます。届出期限は、婚姻の成立日より3ヶ月以内と定められています。なお、ロシア法における婚姻の手続きの詳細については、婚姻相手のロシア人等を通じて関係機関にお問い合わせ下さい。
必要書類
| 婚姻届 2通 | 日本人同士の婚姻の場合は、婚姻前の本籍地と婚姻後選択する新しい本籍により提出部数が異なることがありますので、予め領事班までご相談下さい。 ・婚姻届 ・婚姻届 (記入例: 外国人との婚姻) ・婚姻届 (記入例: 日本人同士の婚姻) ※「婚姻届」は、必ずA3用紙でプリントアウトして下さい。A3以外の用紙で提出された婚姻届は、受理することが出来ません。 ※窓口にもあります。 |
| 戸籍謄(抄)本、全部事項証明、一部事項証明 2通 |
日本人についてのみ
|
| 上外国官憲の発行する婚姻証明書原本 1通 | 当館でコピーをとって原本をお返しします。 |
| 上記婚姻証明書の和訳文 2通 | 翻訳文最下段に、翻訳者を明記して下さい(例:翻訳者:外務太朗)。 |
| 外国人配偶者のパスポート原本 1通 | 当館でコピーをとって原本をお返しします。 |
| 上記パスポートの和訳文 2通 | 翻訳文最下段に、翻訳者を明記して下さい(例:翻訳者:外務太朗)。 |
出生届(子供が生まれたとき)
出生日を含めて3ヶ月以内の提出となります。 出生により外国の国籍も同時に取得している場合、例えば日本人とロシア人の子供がロシアで出生した場合にはロシア国籍も同時に取得しますが、出生後3ヶ月以内に当館を含む在外公館または日本の市区町村役場に出生の届出をしないと、子供の日本国籍は出生時に遡って喪失しますのでご注意ください。
必要書類
| 出生届 2通 | ・出生届 ・出生届(記入例) ※「出生届」は、必ずA3用紙でプリントアウトして下さい。A3以外の用紙で提出された出生届は、受理することが出来ません。 ※窓口にもあります。 |
| 外国官公署発行出生登録証明書若しくは医師作成の出生証明書 1通 |
病院若しくは住所地を管轄する戸籍登録課(ザックス)から発行される証明書原本をご持参下さい。 当館にてコピーをとった後、原本をお返しします。
|
| 上記証明書の和訳文 2通 | 翻訳文最下段に、翻訳者を明記して下さい(例:翻訳者:外務太朗)。 |
| 出生地を証する文書 2通 | 病院で生まれた場合には、病院名および住所のわかる同院ホームページのプリントアウトで可能です。) ※戸籍登録課(ザックス)発行の出生登録証明書にも出生地の記載はありますが、市までの記載であるため同証明書では不十分となります。出生地を証する文書は、住所が番地まで記載されている必要があります。 |
| 上記文書の和訳文 2通 | 翻訳文最下段に、翻訳者を明記して下さい(例:翻訳者:外務太朗)。 |
申出書(外国人配偶者が亡くなったとき)
外国人配偶者が死亡したときは、死亡の事実を知った日から数えて3ヶ月以内に日本人配偶者は、死亡届の代わりに申出書を届けることにより日本人の戸籍に配偶者の死亡の事実を記載しなければなりません。
必要書類
| 申出書 2通 | ・申出書 ・申出書(記入例) ※A4用紙でプリントアウトしてください。 ※窓口にもあります。 |
| 死亡証明書原本 |
当館でコピーを取って原本をお返しします。
|
| 上記証明書の和訳文 2通 | 翻訳文最下段に、翻訳者を明記して下さい(例:翻訳者:外務太朗)。 |
国籍の選択
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、
・18歳に達する以前に重国籍となった場合 ⇒ 20歳に達するまで
・18歳に達した後に重国籍となった場合 ⇒ 重国籍となった時から2年以内
に、どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合には日本の国籍を失うことがありますので注意して下さい。
注)ただし、令和4年(2022年)4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足ります。
注)令和4年(2022年)4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。
国籍選択の具体的な方法についてはこちらをご確認ください。
不受理申出
自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され、戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。(戸籍法第27条の2第3項) 対象となる届書は、届出によって身分行為(身分の取得や変動)の効力が生じる「創設的届出」となる婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届となります。※自身が届出人になる届書についてのみ申出可能。 ただし、外国法により成立した、又は、裁判により確定したことによる「報告的届出」は、この不受理申出をしていても受理されます。
必要書類
| 不受理申出書 2通 | 窓口にあります。 |
| 本人確認書類 |
パスポート等
|
| 法定代理人であることを証明する書類 原本1通、写し1通 | 15歳未満の者について申出を行う場合のみ。 戸籍謄本等。 |
【注意事項】
1) ご本人が直接領事館窓口にお越しください。
2) ご本人が15歳未満であるときは、ご本人に代わってその法定代理人が直接窓口にお越しください。
3) 不受理申出の有効期間は、申出人本人が窓口に出頭して対象の届出をするか、不受理申出の「取下げ」をしない限り、無期限です。
4) 外国籍の方も日本人を相手方とする不受理申出をすることができますが、在外公館では、外国籍の方からの不受理申出を受け付けることはできません。(在外公館で申出できるのは,日本人のみとなります。)
従いまして、外国籍の方は、原則として、日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行う必要がありますが、疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は、(1)申出をする旨、(2)申出の年月日、(3)申出する者の氏名、出生年月日、住所及び戸籍の表示等を記載した公正証書を提出する等で当該申出をする者が本人であることを明らかにすること(戸籍法施行規則第53条の4第4項)により、書面の送付により申出ができる場合もありますので、申出予定の市区町村役場の担当部署に適宜問い合わせてください。